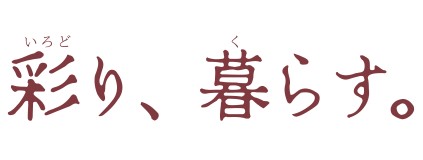長野に暮らす友人から立派な青梅(あおうめ)をどっさり分けてもらった。ありがたい。
かねてより作ってみたかった青梅のジャムに挑戦してみましょう!

青梅ジャムのための鍋がない
1kgもの青梅を「たっぷりの水で」茹でられるような大きな鍋が我が家にはなかった。ああ、いかなごを炊く時に使っていた鍋を捨てるのではなかった。惜しいことをした。と、ちらっと思ったけれど、あれはアルミ鍋だから酸の強い梅には使えない。惜しくともなんともなかった。
仕方なく、ギリギリの水位で茹で始めてみた。完全にこれが間違っていた。アクをとるためになんども水を換えたりする作業が、梅の容量に比して小さい鍋では難しすぎた。果肉を潰さないためにも、水はたっぷり必要なのだった。それに気がついた時には後の祭で、もうこのまま突き進むしかない。
梅のよいかおり
なんとか下茹での工程を終え、果肉をつぶしながら種と分ける作業に入る。ラテックス手袋をはめ、むにゅるむにゅると果肉をこそげとる作業は楽しい。梅のいい匂いにうっとりと包まれて「楽しいな〜」などとのんきに思っていた。この後の惨劇も想像もせず。(種は100gを瓶に入れて100ccの醤油を注ぎ入れておきました。半年ぐらい後には梅の香りのうつった梅醤油が出来上がるので、お刺身や湯豆腐のつゆなどに活躍してもらいます)
次にホーローの鍋に果肉と砂糖を入れて練りつつ加熱する。なぜかわたしのこの22cmサイズのストウブは底の一部が焦げつきやすく、つきっきりでゴムベラでかき混ぜ続けるはめになってしまった。熱々の果肉がはねて火傷するし、かき混ぜているせいでアクを十分に掬えないし、30秒も放置したら焦げ付いてくるしで、大変すぎた。
ほろ苦い青梅ジャム
出来上がったのは、渋みとほろ苦みのあるジャムだった。900ccもできてしまった。どうすればいいのだろう。
青梅ジャムには、アクを抜く最初の下茹でをきっちりやるためにも大鍋が必要だ。大鍋がないのであれば半分量でやるべきだった。500gなら渋いジャムができても「いやぁ失敗しちゃった」と笑えたのに、900ccの大瓶いっぱいにできたのではやっちまった感がひどい。時間の経過とともに苦味が抜けてくれるのを願いつつ、青梅ジャムの瓶をそっと仕舞った。
梅シロップ

残る2kg強の青梅は、梅シロップにすることにした。
今年は母の調子が悪いので、梅シロップを仕込むのもわたしの仕事だ。
1kgの梅なら3リッターの瓶で十分では?などと考えていたが、調べてみると4リッターサイズの瓶のほうが無難らしいとわかった。醗酵する可能性もあるしそれはそうかと納得した。実は6月の頭にザワークラウトを仕込んだら、暑くて醗酵が凄まじいスピードで進み、容器から汁がどばどばと溢れ出してえらい目にあったのだ。
なのでここは素直に4リッターサイズの瓶をふたつ用意した。ひとつは母から借りた。

この写真だとずいぶん余裕があるように見えるが、実物はそうでもない。
我が家は夏季は冷暗所が冷蔵庫以外なくなる。だが、もちろん4リッターサイズの保存瓶ふたつは常温に置くよりない。どうなっちゃうんだろうと心配3割、楽しみ7割で数週間は楽しめそうだ。
梅仕事、もう来年はやりたくない!となるか、それとも来年もぜひやりたいとなるか。毎年丁寧にやっている人はほんとうにマメなんですね…と初めてわかった。梅干しなんて漬け込んだあと、ひきあげて笊(ざる)や盤台(はんだい)に広げて干す工程まである。想像しただけで疲れてしまう。なるほど、だから梅「仕事」なんだな。