人は身体をとおして世界を体験する。
視る、読む、聴く、嗅ぐ、味わう。暑さ寒さや痛みや快感、恐怖を覚えるのも、すべて身体があればこそだ。
キリスト教の神とイスラム教の神は身体を持たない。身体は人間であることの証明でもある。イエスはマリアの母胎を借りて「人の子」として生まれる必要があったし、ムハンマドは預言者として最初から人だ。
逆に言えば、人は自分の身体をとおしてしか世界を体験できない。
他人が感じた熱さをわたしの皮膚が実際に感じることはない。あの人ができる逆上がりをわたしはできないし、宇宙飛行士が船外で活動するときの感覚を味わうこともない。
しかし、わたしたちには想像力と共感力がある。経験から類推する力もある。これらの力が備わっているから、他人の身体を介してあたかも自分もその体験をしているかのような感覚になれる。指先を切った人をみたら「うわ!痛そう」と息がキュッとなるし、楽しそうに踊る人をみたら自分も踊りたくなる。朗々と歌う人の声にうっとりするとき、身体的な快感も必ずある。
こういった体験は個人的かつ感覚的なものだから、言葉にして固定するのが難しい。
高名なバレリーナの踊りをみたり白熱する相撲をみたりして心を震わせたとしても、敢えて語り合うような場でもなければ「感動した」「すごい」でおわってしまう。
それなのに他人の身体の動きになぜわたしたちはなんどでも魅入られ、感動するのか。
思考(言語)と感覚(体験)のあわいを漂うあえかなモノをつかみとる力のある人だけが、ここにひっそりと輝く真実を見せてくれる。
小川洋子はまちがいなくそのうちのひとりだ。
体が動く、とはつまり関節が動くことに他ならない。指先、膝、腰、肩……数々ある関節のうち、彼が最も魅惑的な動きを見せるのは首であると、常々わたしは思っている。首は案外盲点ではないだろうか。首をぐらぐらさせると普通は単にだらしないだけだが、彼の場合、鎖骨が襟元にセクシーな輪郭を浮かびあがらせ、なびく髪先から情熱がほとばしることになる。つまりは、観るものをうっとりさせるのだ。
小川洋子『からだの美』(2023 株式会社文藝春秋)
高橋大輔について書かれた章の一節だけでも、目が開かれる思いがする。
この本は短い何本もの随筆をまとめものだ。アスリートについての章が多いけれど、ハダカデバネズミやゴリラ、赤ん坊の握りこぶしなど、とりあげる体は多岐にわたっている。他人(ヒトではないものを含む)の身体に向けられる視線と、それによって掬いあげられる感覚が絶妙で、かつ、愛に満ちている。慈しみ、驚嘆しながら語られる言葉の連なりは、読んでいて涙ぐむほどだ。
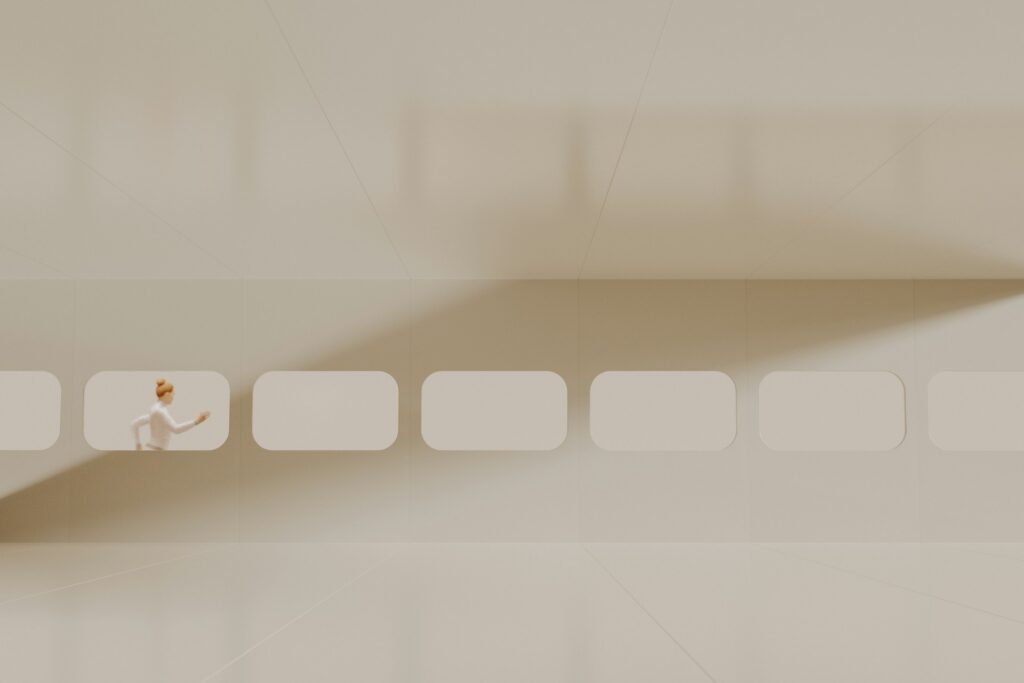
ハダカデバネズミが、小説の中で自分が作り出した動物だったらよかったのに、と考えることがある。(中略)
小川洋子『からだの美』(2023 株式会社文藝春秋)
きっとこの世界のどこかにいるのだろう、と思うけれど、もしかしたら自分が勝手に思い描いた空想かも知れず、それでもなんとなくあきらめきれずに、会えないとはわかっていながら庭の土をスコップで掘ってみたりする。そうして孤独を癒そうとする。
小川洋子の小説が好きで、長めの入院時には何冊も読んだ。
ページを開けばすぐに物語の世界にスッと入ってしまえる。天井の高い石造りの明るい静かな回廊にひとりぽつんと立っているような感覚になる。太陽も見えない、他の建物も人影もない、簡素ですっきりとした白い空間だ。そこで物語をひとり読み進めている感じがする。
派手な乱闘やわかりやすい激情は、小川洋子の作品には書かれない。登場する人たちはみななにかしらの癖やこだわりを握りしめていたり、癒しがたい喪失を抱えていたり、周囲から変わり者とみなされ敬遠されていたりする。静かで、さみしい。そのさみしさが懐かしく、折に触れて読み返す。
なぜその寂寞とした世界に惹かれるのか、この一節を読んでわかった。
孤独だからだ。
自分が孤独を癒すために小説を読んでいるとは思わなかった。誰かの人生や感覚を体験できるのが小説の醍醐味だとばかり思っていた。なぜその体験に魅せられるのかまでは考えたことがなかったのだ。
身体があるからこそ三次元を生きられる。バーチャルリアリティの技術がどれほど発達しようと、最低でも脳と神経が必要だ。
皮膚を境界線とする身体を生きるわたしたちは、母親の胎内から生まれ落ちた時から死ぬ時まで、誰かと完全に「一体に」なることなどできない。
誰もが孤独なひとつの個体だ。
互いの孤独な身体をみつめ、共感し想像し追体験することで、わたしたちは孤独を薄めようとしているのかもしれない。

