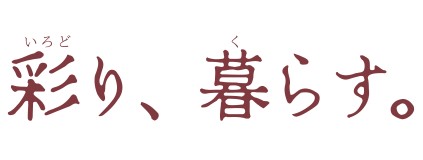味覚はおそらく千差万別で、特定の味への感受性は人によって様々だろうと思う。
たとえば辛味が苦手な人は、料理に含まれる辛味に敏感だ。でも、敏感かどうかとおいしく感じるかどうかはまた別である。「辛いのは苦手だが、わさびがなければ物足りない」とか「辛いの大好き。だけどなんでも辛くしたいわけではない」とかは、矛盾しない。
わたしは極端に苦味と渋味が不得手で敏感だ。特に苦味はだめだ。あれはいけない。
貝、魚のワタ、芽キャベツ、チコリ、柑橘類の皮の苦みはもちろんのこと、納豆をはじめ大豆製品に残る苦味すら憎んでいる。作った文旦ピールのほとんどは父の胃袋に消えた。コーヒーも牛乳なしではあまりそそられない。
春はほろ苦い野菜だらけ
春先に出回る野菜はほろ苦いものばかりだ。菜の花、ふきのとう、筍、ウド、タラの芽、うすいえんどうなど、芽や種(豆)は苦い。新じゃがにすらほろ苦さとえぐみがある。

自分ひとりが食事当番の自炊生活では、不得手な食材はまったく手に取らなくなる。苦い野菜をとことん避けて暮らして何十年…なのだけれど、ここにきて変化が訪れた。
パセリ
数年前に【ハムマーマレードとパセリサンド】に出会い、パセリのおいしさに目覚めた。
香味野菜としてのパセリはたいへん優秀だ。捨てるところがない。葉はそのまま食べられるし、茎は洋風の出汁をひくときにいれると風味がよくなる。入れると入れないとでは全くの別物といっていい。偉そうに言ってるけど最近気がつきました。
生協で毎週のようにパセリを注文している。届いたらすぐに洗って葉と茎を分け、葉はサラダスピナーでよく水気を切ってからざくぎりにし、半分をレモン汁とオリーブオイルで和えておく。これは生で食べる用で、サラダやちょっとした付け合わせに活躍する。半分はそのままタッパーに入れ、スープやチャーハン、パスタ、スクランブルエッグなどにどっさり使う。
パセリの苦さと匂いは、香味野菜のなかでもマイルドな部類だからわたしでもおいしく食べられるのだろう。
パセリに150円だすならきゅうり2本買うわいとなる気持ちもわかる。が、春から初夏にかけてのパセリをぜひ試してみてほしい。ちょっと感心するほどおいしいから。
天敵、春菊
芽キャベツと春菊はわたしの天敵で、あの匂いと苦味とえぐみには憤りを覚えるほどだ。
すき焼きや鍋ものに春菊をいれられたが最後、どれほど空腹でもわたしはそっと食卓を去る。
かくも苦手な春菊だが、関西にいたころは「春菜」なら食べられた。関西の「春菜」はいわば春菊のお上品バージョンである。強烈な匂いやえぐみがほとんどない。とはいえ、「これなら食べられるわ」というだけで、好んで食べたいものではなかった。
話はズレるが、関西暮らしの中で、鍋物には必ずしも長ネギを入れなくてもよいと知って衝撃を受けた。京阪神ではネギといえば青ネギ、細ネギが主流で、こまかく切ったものを薬味とする。鍋の中で他の具と煮込まないのだ。自分は鍋に長ネギを入れるのが実は苦手だったんだと気がつき、爾来、わたしは鍋物に長ネギは入れない。(ただしほうとうを除く)
話を春菊に戻そう。
先日、朝のウォーキングの帰路でふわっふわでおいしそうな春菊を庭先販売でみつけてしまった。200gほど入って100円。しかも露地物だ。いや…春菊だろ?と一瞬躊躇ったがなぜか衝動的に買ってしまった。
帰宅後、よく水で洗ってからナムルにしてみた。ニンニクや鶏ガラスープの素は入れていない。味付けは茹でる時の塩と、小さじ1の醤油と胡麻油のみ。

これがとてもおいしい。なんで。どういうこと。
もしかしたら、春菊も昔とは変わり食べやすい味になってきているのかもしれない。そういえばトマト、ピーマン、人参も昔より食べやすくなった。品種改良もさることながら、育て方などにも生産者が工夫を重ねて、より美味しくなっているのだろう。
それにひきかえ里芋はしっかりした肉質の、おいしいものに出会えなくなった気がする。野菜にも流行があるようだけど、おいしい野菜が庶民でも気軽に食べられる国であってほしい。